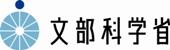文字
背景
行間
日誌
子供の心に寄り添う教師が求められているのですが・・・
9月2日付け下野新聞『日曜論壇』に掲載された、獨協医大公衆衛生学教授小橋元(げん)氏の「心に寄り添い救う社会に」を読んで感銘を受けました。
小橋氏は、学生時代に多くの治らない患者と接したことから、病気になる前の予防を考えるようになったといいます。そして、臨床の場で病気の予防ができるのは、産科の妊婦検診と母親教室と気付き、産婦人科医になることを決心します。しかし、自分が男である以上、産婦人科を受診する女性の気持ちは分からないことを知り、愕然とします。そこで氏は、少しでも女性の気持ちを分かろうとして自ら試みたことを次のように書いています。
私は、夜中の誰もいない分娩室で分娩台に上がってみたことがある(もちろん下着も取って)。また、初めて働く病院では、いつも朝早く病院の正面玄関から受付を通って外来へ行き、待合室のベンチに腰掛けてみることが習慣だった。たとえば外来で昨晩からの腹痛で来院した患者さんに会ったとき、「昨晩からどんな気持ちで過ごして、今朝はどんな気持ちでどんな景色を見ながらこの外来に訪れたのだろう」と具体的にイメージしながら診察をする。患者さんと同じ境遇にはなれないが 「患者さんの心に寄り添おうとす」る気持ちが、患者さんの不安を和らげ、患者さんを救うと信じていた。
体験しなければ分からないことがあります。と言っても、絶対に体験できないこともあります。その最たるものが男性が妊婦になることでしょう。しかし小橋氏は、自ら分娩台に、しかも下着を取ってまでして乗るなど、患者と同じ状況に自らを置くことを試みます。もちろんそれで、患者の気持ちが理解できるということではありませんが、そうすることが「患者の心に寄り添う」気持ちの表れで、それがあるからこそ患者の不安を和らげ救うことができるというのです。なんとすばらしいことでしょう。医者の鑑と言えます。
翻って、教師も今ほど子供に寄り添う指導が求められているときはないでしょう。しかも、小橋氏とは違って、どの教師も子供時代があって学校生活を経験しているのですから、子供の境遇が分かるはずです。にもかかわらず、教師になった途端に子供の立場を忘れ、「指導」という美名の下、多少難しいことでも一律に子供に強いる教師がいます。
かつてのように「子供の共通性を前提とする学校」であればそれでも通ったかもしれませんが、今や学校は、「子供の多様性に応答する学校」への転換が求められているのです。だからこそ、子供の心に寄り添う教師であってほしいと思っています。
小橋氏は、学生時代に多くの治らない患者と接したことから、病気になる前の予防を考えるようになったといいます。そして、臨床の場で病気の予防ができるのは、産科の妊婦検診と母親教室と気付き、産婦人科医になることを決心します。しかし、自分が男である以上、産婦人科を受診する女性の気持ちは分からないことを知り、愕然とします。そこで氏は、少しでも女性の気持ちを分かろうとして自ら試みたことを次のように書いています。
私は、夜中の誰もいない分娩室で分娩台に上がってみたことがある(もちろん下着も取って)。また、初めて働く病院では、いつも朝早く病院の正面玄関から受付を通って外来へ行き、待合室のベンチに腰掛けてみることが習慣だった。たとえば外来で昨晩からの腹痛で来院した患者さんに会ったとき、「昨晩からどんな気持ちで過ごして、今朝はどんな気持ちでどんな景色を見ながらこの外来に訪れたのだろう」と具体的にイメージしながら診察をする。患者さんと同じ境遇にはなれないが 「患者さんの心に寄り添おうとす」る気持ちが、患者さんの不安を和らげ、患者さんを救うと信じていた。
体験しなければ分からないことがあります。と言っても、絶対に体験できないこともあります。その最たるものが男性が妊婦になることでしょう。しかし小橋氏は、自ら分娩台に、しかも下着を取ってまでして乗るなど、患者と同じ状況に自らを置くことを試みます。もちろんそれで、患者の気持ちが理解できるということではありませんが、そうすることが「患者の心に寄り添う」気持ちの表れで、それがあるからこそ患者の不安を和らげ救うことができるというのです。なんとすばらしいことでしょう。医者の鑑と言えます。
翻って、教師も今ほど子供に寄り添う指導が求められているときはないでしょう。しかも、小橋氏とは違って、どの教師も子供時代があって学校生活を経験しているのですから、子供の境遇が分かるはずです。にもかかわらず、教師になった途端に子供の立場を忘れ、「指導」という美名の下、多少難しいことでも一律に子供に強いる教師がいます。
かつてのように「子供の共通性を前提とする学校」であればそれでも通ったかもしれませんが、今や学校は、「子供の多様性に応答する学校」への転換が求められているのです。だからこそ、子供の心に寄り添う教師であってほしいと思っています。