校長室から
奮闘!物部中特設駅伝部
今日、10月27日、好天に恵まれた爽やかな秋の日に、芳賀郡市駅伝競走大会が行われました。
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、例年会場となっている井頭公園ではなく、真岡市陸上競技場のトラックを使って、たすきを使用しない区間ごとのタイムレースでの実施となりました。
我が物部中学校は、3年ぶりに男女アベックで出場し熱い走りを披露してくれました。
たすきはなくても、コンマ1秒でもタイムを削り、次につなごうとと全力疾走する姿に胸を打たれました。
コロナ禍の中、十分な練習時間を確保できませんでしたが、それを補うように気持ちを込めて、仲間のため、チームのために、必死に前走者を追ってくれました。
結果は、男子9位、女子10位と惜しくも入賞を逃しましたが、選手はもちろん応援の生徒も含め、誰一人あきらめない物部中らしい走りができたと思います。
特設駅伝部の健闘を心から称えたいと思います。
特に、3年生は、今年のスローガンである「物中進化~限界への挑戦~」を体現するような素晴らしい走りでした。
3年生はこれで引退となりますが、皆さんの熱い思いは必ず後輩たちが引き継ぎ、いつしか物部中の伝統となっていくことでしょう。
そして、物部中が進化する推進力となってくれることを信じています。
特設駅伝部の選手諸君、本当にありがとう。
そして、応援に駆けつけてくれた保護者の皆様、ありがとうございました。
奮闘の様子は、後日保護者ページにアップさせていただきます。楽しみにお待ちください。
桜町祭 感動をありがとう
本日、物部中学校文化祭「桜町祭」を実施しました。
コロナ禍の中での実施ということもあり、学年展示や売店、バザー等を中止し、入場者についても生徒一人につき保護者等1名とさせていただきました。
代わりに新しい試みとして、ビデオ通話アプリによる配信を実施したところ、50人以上の皆様に御視聴いただき、大変うれしく思っております。
制約が多い中での桜町祭ではありましたが、生徒たちは例年にも増して熱心に取り組み、多くの感動を届けてくれました。
・練習が始まった頃はどうなるかと思った合唱コンクール
→ 今日の本番は、見違えるような上達ぶりを披露できました。
特に、3年生の渾身の合唱は、会場を感動の渦に巻き込みました。
・本当に終わるのか、本番に間に合うのか不安だった全校制作の「折り鶴文字」
→ 幕が開いたときのどよめき。努力が結実した瞬間でした。
約五千羽。よく折りました。よくつなぎました。
・個人発表の部、参加者は本当に集まるのか。盛り上がりに欠ける不安も
→ 新企画3年生ダンスは、笑いあり、憧れあり、筋肉ありと見事に才能開花
事前審査を突破した個人発表のクオリティにも驚きました。
最後の尊徳太鼓、保存会の皆様とのコラボもあり、しびれました。
・コロナ禍の中、本当に桜町祭が実施できるか不安、入場制限もきつい
→ コロナ対策班・ZOOM班大活躍、安全・安心な桜町祭になりました。
御家庭にもたくさんの感動を届けることができました。
そのほか、少年の主張、生徒会ムービーなどなど盛りだくさんの内容で、半日での実施がもったいないくらいでした。
コロナ禍の中、「心化 ~体は遠く、心は近く~」をメインテーマとした桜町祭は、絆、躍動、笑顔、涙、思いやり、感動などが宝石のようにちりばめられ、生徒にとって貴重な成長の場となりました。
桜町祭により、さらに「心化(進化)」した物部中学校は、コロナに負けずこれからも新たな歴史を刻み続けます。
応援、よろしくお願いいたします。
歌声響く学校
桜町祭のメインイベント、合唱コンクール
本番に向けて、少しずつ大きくなってきた練習の歌声
桜町祭前日の今日、学校中に気持ちのこもった美しい歌声が響き渡っています。
それは、成長の足跡でもあります。
練習が始まった頃は、うまくいかずに衝突したことや諦めそうになったこともあったでしょう。
パート内やパート間の対立もあったかもしれません。
しかし、気付いたはずです。
合唱は、仲間を信じ、互いの足りないところを補い合うことが、何よりも大切だと言うことを。
君たちは今日まで、多くの困難を乗り越えて、大きく成長してきました。
明日本番を迎える君たちに、有名なペップトーク(スポーツ選手を励ますために、指導者が試合前などに送る短い激励のメッセージのこと)を紹介します。
昨年のラグビーワールドカップ日本大会で、ジェイミー・ジョセフヘッドコーチが、当時世界ランキング1位のアイルランドと対戦する日本代表に送った言葉です。
誰も我々が勝てるとは思っていない。
接戦になるとすら思っていない。
君たちがどれだけハードワークをしてきたか誰も知らない。
君たちがどれだけ犠牲を払ってきたかも知らない。
でも君たちは、自分たちが準備できていることを知っている。
私も君たちが準備出来ていることを知っている。
よし、行くぞ!
明日の合唱コンクール、楽しみにしています。
人皆に美くしき種子あり 明日何が咲くか
はきだめに えんど豆咲き 泥地から 蓮の花が育つ
人皆に美くしき種子(たね)あり 明日何が咲くか
これは、安積得也さんの「明日」という詩です。子供たちの限りない可能性に期待する作者の思いが込められた、すばらしい詩だと思います。
安積さんは、詩人としてだけではなく、官僚や栃木県知事(官選)、社会評論家など多方面で活躍された方です。また、明治、大正、昭和、平成と4つの時代を生き抜いた方でもあります。
子供たちは様々な可能性の種子を秘めていますが、そこから咲く花は一つとして同じ形や色のものはなく、花の咲く時期も異なります。
しかし、必ず花は咲きます。
この詩に接して、改めて、教師の仕事は子供たちが持っている可能性を信じ、様々な支援をしながら、辛抱強く開花を待つことなのだと感じました。
生徒の皆さんも自身の中にある可能性の種子を信じ、努力してほしいと思います。
いよいよ、あと3日で、桜町祭です。それぞれの花を咲かせましょう。
世界食料デー
今日、10月16日は、「世界食料デー」です。
世界食料デーのテーマに毎年テーマがあり、今年は、「育て、養い、持続させる。共に。―未来をつくる私たちのアクション―」です。
今、世界では、すべての人が食べられるだけの食料は生産されているのに、9人に1人が十分に食べられていません。
8億人以上の人々が飢えに苦しみ、5秒に一人の割合で子供が餓死しています。
日本も含む国際社会は、2030年までに「飢餓をゼロに」することを約束しましたが、さまざまな課題が相互に関係し合い、複雑になっている飢餓や食料問題の解決には、まだまだたくさんの人の協力が必要です。
日本では、年間2,550万トンの食品廃棄物等が出されています。このうち、まだ食べられるのに廃棄される食品、いわゆる「食品ロス」は612万トンです。
これは、世界中で飢餓に苦しむ人々に向けた世界の食糧援助量の1.6倍に相当します。
食品ロスを国民一人当たりに換算すると"お茶腕約1杯分(約132g)の食べもの"が、毎日捨てられていることになるのです。
自分が食に困ってないからよいのではなく、世界中の全ての人が満足に食べられるようにしなければなりません。
物部中の学校経営理念は、「『地域貢献』『国際貢献』を合い言葉に、二宮尊徳先生の教えが今なお息づくふるさと物部を愛し、夢を持って、広く国際社会で活躍できる生徒を育成すること」です。
中学生の自分にできることは何なのか。一緒に考えていきましょう。

読書の秋
10日(土)の下野新聞に、若者の読書離れの記事がありましたが、アンケートによると、月に1冊も本を読まない中学生の割合は16.1%と非常に高い結果となりました。
本校でも朝の読書や読み聞かせ、学校図書館司書からの啓発など、様々な方策により読書活動を推進してるところです。
そのようなこともあり、本日、10月14日(水)の全校朝会では、読書の意義や必要性について話をしました。
主な内容は、以下のとおりです。
・読解力や想像力、思考力、表現力等が養われる。
・多くの知識を得たり、多様な文化を理解したりすることができる。
・自ら学ぶ楽しさや知る喜びを体得し、更なる探究心や真理を求める態度が培われる。
・読書をすることで自分の世界が広がるとともに、進むべき方向が明確になり、豊かな人生を送ることができる。
また、講話の最後に、学級担任のおすすめの図書を紹介しました。今週中には、全職員分を一覧表にしてお配りします。
同じ本でも読む時期によって感じ方が変わり、感受性の強い思春期の今しか感じられないことがたくさんります。
中学生の今だからこそ、様々なジャンルの本を数多く読んでほしいと思います。
秋の夜長、良書に親しむよい機会としてください。
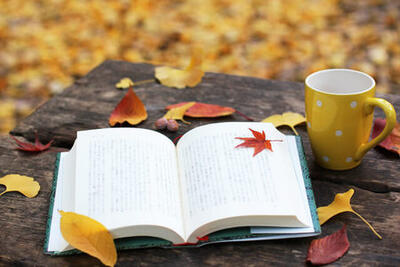
童謡「赤とんぼ」
秋も日に日に深まり、赤とんぼを目にする機会も増えてきました。
赤とんぼと言えば、童謡「赤いとんぼ」(作詞:三木露風 作曲:山田耕筰)を思い出します。
♪ 夕焼け小焼けの赤とんぼ 負われて見たのはいつの日か
山の畑の桑の実を 小かごに摘んだはまぼろしか
十五で姐(ねえ)やは嫁にいき お里の便りも絶えはてた
夕焼け小焼けの赤とんぼ とまっているよ竿の先 ♪
恥ずかしい話ですが、つい最近まで、「負われて見た」の部分を「追われて見た」だと思い込んでいました。
ということは、全体の意味を正しく理解していなかったことになります。
この歌詞は、竿の先にとまっている赤とんぼを見て、幼少期を回想する内容です。
子守として雇われていた「姐や」に背負われて赤とんぼを見たことなど、幼少期の思い出がつづられています。
作詞者自身の思い出とのことですが、幼少期の複雑な境遇もあり、様々な感情が込められているようです。
歌詞の意味が理解できると、一層心にしみる童謡となりますね。
童謡とともに深まりゆく秋を感じると、感性が磨かれます。
その思いを詩や俳句にしてもいいですね。
鉄は熱いうちに打て!
先週1・2日に行われた中間テストの結果は、もう返却されたでしょうか。
計画的に学習に取り組んだ人は好結果だったでしょうし、前日に慌てて勉強した人は残念な結果だったかもしれません。
いずれにしても、なにがしかの課題は見つかったはずです。
「鉄は熱いうちに打て!」ということわざがあります。
意味は、「人は柔軟性のある若いうちに鍛えることが大事だ。」、「物事は時機を逃さないように実行しないと成功しにくい。」というものです。
中間テストの結果が返却されたばかりの今は、まさに「熱い」状況です。
この時機を逃さず、日々の学習に気持ちを込めて取り組んでください。
「鉄は熱いうちに打て!」頑張れ、物中生!
音楽の力、チーム物部とともに
10月3日(土)、井頭公園で芳賀地区中学校吹奏楽フェスティバルが開催され、本校も演奏順1番で、見事な演奏を披露しました。
決して多いとは言えない部員数であり、なおかつ、今年度は新型コロナウイルス感染症の影響で練習環境が十分ではない中ではありましたが、練習の成果を存分に発揮したすばらしい演奏でした。
特に、3年生は3年間の思いを込めた演奏で、聴衆に多くの感動を与える内容になったと思います。
まさに、人々を元気付け、明日への希望につながる「音楽の力」を感じたところです。
また、フェスティバルにはPTA会長様をはじめ多くの保護者の皆様方、3年生を中心とした有志の生徒たち、そしてほとんどの教職員が応援に駆け付けるなど、「チーム物部」の絆を感じることができました。
本校は、今後も人と人との固い絆の下、生徒たちの夢を育んで参ります。
神無月
いよいよ今日から10月です。2学期中間テスト、初日のできはいかがだったでしょうか。
さて、10月は「神無月(かんなづき)」とも呼ばれます。月を数字で表すようになったのは、明治の初め頃に新暦が採用されてからのことです。
旧暦では、和風月名(わふうげつめい)と呼ばれる月の和風の呼び名を使用していました。和風月名は旧暦の季節や行事に合わせたもので、現在の暦でも使用されることがありますが、現在の季節感とは1~2か月ほどのずれがあります。
ちなみに「神無月」の由来には、諸説ありますが、10月は全国の八百万の神様が、一部の留守神様を残して出雲大社へ会議に出かけてしまい神様がいないので「神無月」、反対に出雲の国(島根県)では神様がたくさんいらっしゃるので「神在月」という説があります。また、他には「神無月」の無を"の"と解して「神の月」とする説もあります。
いずれにしても、ただの数字よりは趣があり、日本人の豊かな感性を感じるところです。
なお、本日は「中秋の名月」。テスト勉強の合間に満月を眺め、疲れを癒やしてみてはいかがでしょうか。
輝く命、つながる命
自分の番 いのちのバトン 相田みつを
父と母で二人
父と母の両親で四人
そのまた両親で八人
こうしてかぞえてゆくと
十代前で千二十四人
二十代前では—?
なんと百万人を越すんです
過去無量の
いのちのバトンを受けついで
いまここに
自分の番を生きている
それが
あなたのいのちです
それがわたしの
いのちです
世界でたった一つのかけがえのない自分の命、どうか大切に
人も動物も幸せに
明日26日で、動物愛護週間(9/20~26)が終わります。
動物愛護週間は、法律によって、「ひろく国民の間に命あるものである動物の愛護と適正な飼育についての関心と理解を深めるようにするため」に設けるよう、定められているものです。
ペットとして犬や猫を飼われている方も多いと思いますが、そのほとんどの方は家族として愛を注ぎ大切にされています。
しかし、中には心ない人もいて、新しく生まれた小さな命を含め、「捨て猫、捨て犬」が見られます。
飼い主が見つからない犬や猫は、動物愛護センターで一時保護されます。そして、一定期間新しい飼い主を探しますが、どうしても見つからなければ、最後は殺処分となります。
殺処分の件数は、年々減ってきてるとはいえ、昨年度だけで3万匹以上の犬や猫が殺処分されています。
殺処分に関わっているある獣医さんは、「動物の命を助けたくて獣医になったのに、動物の命を奪うことになるなんて…」と悲痛な胸の内を吐露しています。
ドイツは、殺処分ゼロを実現してると言われています。
「日本に生まれなければよかった」
動物たちにそう言われないよう、人も動物も幸せに暮らせる社会を実現していきましょう!
今しかできないこと
先週、9月17・18日に修学旅行を実施しました。
コロナ禍の中での修学旅行ということもあり、方面を福島・那須に変更し、期間も一泊二日としました。
旅行中は生徒の健康・安全を最優先に考え、最新式のエアコンを搭載した観光バスの利用や手指の消毒の徹底、こまめな検温などを実施しました。
幸い発熱やかぜの症状のある生徒もなく、全員が無事に修学旅行を終えることができました。
3年生の明るさ、素直さ、前向きさにより、例年にも増して収穫の多い修学旅行になりました。
改めて3年生の確かな成長と強い絆を感じることができ、心からうれしく思います。
今回は修学旅行の実施自体が危ぶまれたところですが、一泊二日とはいえ、無事実施することができて、本当によかったと思います。
もちろん旅行はいつでも行けますし、高等学校等にも修学旅行はあります。しかし、小中9年間一緒だった仲間との旅行は今回が最後です。友情も一層深まったことと思います。
物事には「今しかできないこと」があります。
特に、感受性の強い思春期には、よりたくさんの「今しかできないこと」があると思います。
あのとき、あの仲間とだからこそ感じられることがあり、それは成長の確かな礎になります。
コロナ禍の中ではありますが、生徒の健康・安全を最優先しつつ、「今しかできないこと」を体験させられるよう、本校は学校行事等にも可能な限り取り組んで参ります。
謙虚な気持ち
棋士の藤井聡太八段が、手が付けられないなほどの強さを発揮し、快進撃を続けています。
7月16日に棋聖戦を制しタイトル獲得最年少記録を更新、また、8月20日に王位を獲得し史上最年少でのタイトル二冠保持と八段への昇段を果たすなど絶好調です。
まさに伸び盛りの藤井聡太八段ですが、タイトル戦の報道を見てとても印象に残ったシーンがあります。
それは、対局が終わった後の深いお辞儀です。目の前にある将棋盤よりさら深く頭を下げています。
負けたときは潔く、勝ったときは相手への敬意を表しより深くお辞儀をする。
将棋と対戦相手に礼を尽くす姿に、謙虚さを感じます。
謙虚な人は大きく伸びます。
「我以外皆我師」
謙虚な気持ちで、学ぶ心を大切にして、大きく大きく伸びましょう。
がんばれ物中生!
ファーストペンギン
本日、9月10日(木)、9月の全校朝会を行いました。
初めに、2学期学級委員の任命を行いましたが、そのやる気に満ちあふれた表情に頼もしさを感じました。
今後、桜町祭など大きな行事も控えています。2学期学級委員には、学級の中心となって活躍してくれることを期待しています。
次の校長講話では、運動会の振り返りを行ったあと、「ファーストペンギン」の話をしました。
主な内容は以下のとおりです。
魚を獲りたいペンギンは、海の様子をじっと観察するのですが、海の中にはペンギンの天敵であるシャチやアザラシなどもいるため、最初はなかなか飛び込もうとはしません。しかし、しばらくすると、あるペンギンが意を決して最初に飛び込みます。天敵に捕食されるリスクをものともせず、自分を信じてチャンスをつかもうとするこの勇気あるペンギンを「ファーストペンギン」と呼びます。そして、誰かが先人を切って飛び込めば、後に続いて次々と海に飛び込んでいきます。
「ファーストペンギン」は、天敵に食べられてしまうリスクはありますが、反面、誰よりも先にエサにありつき、おなかいっぱい食事をするチャンスを得ることができます。それだけではなく、仲間が安心して海に入ることができる状況をつくることで、群れに大きく貢献します。
学校生活においても、先生に何かを求められたときに、最初に手を挙げるのは難しいいことです。しかし、勇気を出して、手を挙げてファーストペンギンになれれば、自分の新しい可能性を引き出すことができます。
普段の生活でも、ファーストペンギンになることで、今まで見たことのない新しい世界を知るきっかけとなり、人生をより豊かなものにしてくれることでしょう。
皆さんが、最初の1歩を踏み出す勇気をもってファーストペンギンになってくれることを期待しています。頑張ってください。
3年生の底力
本日、9月5日(土)に秋季大運動会を実施しました。
今年は、新型コロナウイルス感染拡大を受け、生徒の健康安全を最優先に考え、内容を大幅に見直し時間を短縮して実施しました。
また、御来賓や地域の皆様方の参観を御遠慮いただき、各家庭2名までと入場制限もさせていただきました。
そのように制約が多い中での運動会でしたが、生徒たちはすべての演技に一切手を抜くことなく全力で取り組みました。
そこには、多くの喜びや笑顔、涙、感動がありました。
まさに、99名の生徒一人一人が主役の運動会、それぞれの個性をいかんなく発揮していました。
特に、3年生の頑張りには目を見張るものがあり、物部中の顔として、大いに運動会を盛り上げてくれました。
3年生のあまりの頑張りに、帰りの会にお邪魔してお礼を述べさせてもらったほどです。
コロナ禍の中で学校行事を実施する時間を生み出すことも容易ではありませんが、今日の運動会後の生徒の表情を見ていると、やはり学校行事は重要だということを再認識しました。
発展途上にある生徒たちは、それぞれの学校行事を節目として階段を1段上がるように成長していきます。
勝利を目指して奮闘すること、新しい役割に挑戦すること、係の仕事を責任をもって行うこと、喜びを分かち合うこと、涙する友人を慰めること、声を枯らして応援することなど、様々な経験が人を成長させます。
物部中学校はこれからも学校行事に力を入れて取り組んで参ります。
本日、応援に駆けつけてくれた保護者の皆様、検温や片付け等をお手伝いいただいたPTAの役員や係の皆様、本当にありがとうございました。
ソーシャルディスタンスは思いやり
昨日、運動会予行を実施しましたが、突然の豪雨によりずぶ濡れになった生徒を午後帰宅させました。
保護者の皆様には、急な変更で御迷惑をお掛けしたと思いますが、生徒の健康を第一に考えての判断ですので、御理解いただきたいと思います。
さて、予行練習中、何度も「ソーシャルディスタンス、もっと離れて!」という指示が出ていました。
今年の運動会は、新型コロナウイルス感染症対策を行いながらの実施であり、当然例年とは違った内容が求められています。
生徒は例年との違いにと惑いながら、教職員もどこまで配慮すれば安全か悩みながらの予行練習となりました。
ところで、新型コロナウイルス感染症対策で他人と距離を取ることを「ソーシャルディスタンス」と言います。直訳すると「社会的距離」となります。
一般的に他人と距離を取る場合は、相手が嫌いなときや怖いときなどマイナスのイメージがあります。
しかし、コロナ禍の中での社会的距離は、みんなで安全に生きていくために保つ距離のことです。
ソーシャルディスタンスは、「あなたのことが大事だから離れています。」という思いやり、優しい気持ちをもって使う言葉です。
「ソーシャルディスタンスだね。」と言って友達が離れたら、「ありがとう。」と応える。
そんな思いやりあふれる社会は、とても素敵だと思います。
ソーシャルディスタンス等、新型コロナウイルス感染症対策に配慮した明日の運動会、御期待ください。
命を守る行動を
今日、9月1日は「防災の日」です。
防災の日とは、「台風、高潮、津波、地震等の災害についての認識を深め、それらの災害に対処する心構えを準備するため」の啓発日です。
9月1日の日付は、1923年(大正12年)に発生した「関東大震災」に由来しています。関東大震災では、相模湾一帯を震源とするマグニチュード7.9の巨大地震により、死者・行方不明者は約10万5千人、建物の全半壊・焼失は約37万棟と関東一円に大災害がもたらされました。
日本はプレートの境目に位置しており、ひずみのエネルギーがたまれば必ず巨大地震が起きます。
政府の地震調査委員会は、関東大震災と同様の首都直下地震が、今後30年以内に70%の確率で起きると予測しており、今後も油断は禁物です。
加えて、近年全国各地で起きているの豪雨被害も心配されるところです。地震と違い台風や豪雨はある程度予測できます。自治体の避難情報を受けて迅速に行動することが重要となりますが、報道によると、分かりずらかった「避難勧告と避難指示の違い」も、避難指示に一本化される見通しです。
いずれにしても、災害発生時には「的確な判断」と「迅速な行動」により自らの命を守ることが何より大切です。
本校でも、避難訓練の充実等により災害発生時に自らの命を守る力を身に付けさせたいと思います。
【関東大震災のときにも発生したと思われる火災旋風】
冒険家の心意気を
今日、8月30日は、「冒険家の日」と呼ばれています。
それは、以下の冒険が全てこの日の前後に行われたことに、由来しています。
・1965年、同志社大学の遠征隊による世界初となるアマゾン川源流からのボート下りの成功
・1970年、冒険家の植村直己による北アメリカ最高峰マッキンリー(6194m)単独登頂成功
・1989年、海洋冒険家の堀江謙一による世界最小の外洋ヨットで太平洋単独横断成功
植村直己さんは、「エベレスト日本人初登頂」、「世界初の五大陸最高峰登頂者」、「犬ぞり単独行としては世界で初めて北極点に到達」など、冒険家として数々の偉業を成し遂げています。
「冒険とは生きて帰ること」と言っていた植村さんですが、1984年2月に「マッキンリー冬期単独登頂(世界初)」を成功させたあと消息が途絶え、下山することはありませんでした。
植村さんの偉業を称え、1984年4月に国民栄誉賞が授与されています。
生前、冒険家として活躍した植村さんは数々の言葉を残しています。
「みんな、それぞれが、何か新しいことをやる、それはすべて冒険だと、僕は思うんです。」
「必ず壁はあるんです。それを乗り越えたとき、パッとまた新しい世界がある。」
冒険に挑み、新しい世界を知る。物中生の新たな挑戦を楽しみにしています。
風はすべて追い風
「風はすべて追い風。わたしがどこを向くかだ。」
2014年、某ファッションビルのキャッチコピーです。
人生の中で、ときには「向かい風」を強く感じることがあると思います。
でも、少し向きを変えるだけでずいぶん進みやすくなりますし、180度向きを変えれば、完全な追い風です。
「初志貫徹」とは相いれない言葉かもしれませんが、本当につらいときは、視点を変えて「追い風」を探してみるのもいいかもしれません。
何かうまくいかないときは、他のことを試してみる、そんな柔軟性も必要です。
自分を変えてみれば、また違った景色が見えてくることもあるでしょう。
「風はすべて追い風。わたしがどこを向くかだ。」
がんばれ物中生!























