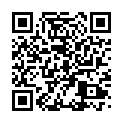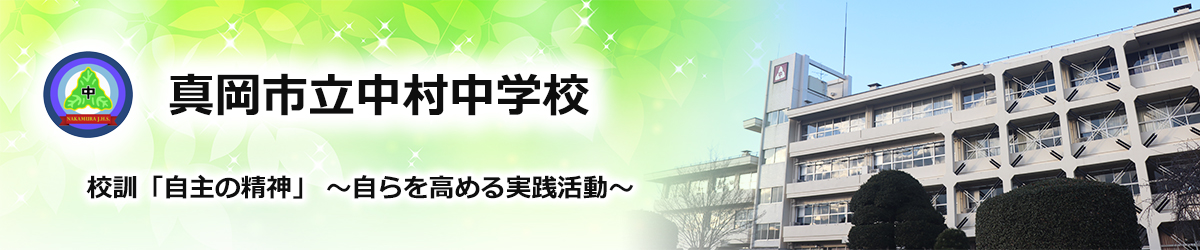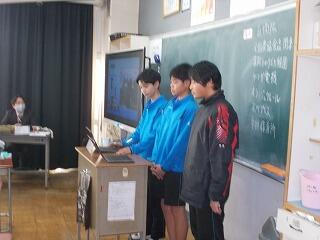校長室から
【校長室よりNo.179】なんて素敵な日なのでしょう
今日の卒業式の予行に続いて、同窓会入会式を行いました。その後、3年生が用事があるからと迎えに来ました。体育館に行くと、卒業を控えた3年生から私への「卒業証書授与式」を執り行って下さいました。生徒会長手書きの卒業証書を手渡され、そのあと各クラスからのお手紙を代表の方からいただきました。思いもよらぬサプライズでした。このHPでも常々、中村中学校生徒の心の温かさについて触れてきました。ただ辞めていくだけの他人にここまでしてくれる心優しき生徒たち。本当に幸せな教員人生だったと自信を持って言えます。「なんて素敵な日なのでしょう。」
【校長室よりNo.178】陽だまりの中で
本日は卒業式の予行練習を行いました。いよいよ来週の月曜日は卒業式です。卒業式の式辞の中でも述べますが、中村中の生徒たちは、昼休みに本当によく遊びます。多くの生徒がどんなに寒くても校庭に出て、スポーツや語らいの中で級友との時間を楽しんでいます。そんな「陽だまりの中」で遊ぶ生徒たちの姿を見る時間は、私たち教師にとっても至福の時間でした。月曜日の卒業式は、今のところの天気予報では、晴れで暖かい日になりそうです。
【校長室よりNo.177】五感を研ぎ澄ます
先日、雪の日にご紹介した正門前のしだれ梅の花。木の下に行くと、なんとも言えない、甘酸っぱい香りが漂っています。情報化や効率化が進み、誰もが「忙しい」日々を過ごしています。しかし、その忙しさの中でも、五感を研ぎ澄ませて、様々なものを感じる「心のゆとり」は持ち続けたいものだと感じます。学校においでの際は、ちょっとだけ「心のゆとり」をもって、梅の花の香りを味わってみて下さい。
【校長室よりNo.176】季節は巡る
下の写真は正面玄関前にある「かしわ」の木です。昨年も同様の時期にこのHPで紹介させていただきました。このかしわの木は、冬のこの時期、一見枯れてしまったように見えますが、実は新芽が出てから古い葉が落ちるようです。この性質から、「家系繁栄」や「子孫繁栄」を願って五月の節句に柏餅を食べるとも言われています。昨年の同時期のHPを見返して、季節が巡っていることを実感するとともに、かしわの葉のように、中村中の歴史と伝統が一時も途絶えることなく、確実に引き継がれていくことを願います。
【校長室よりNo.175】組織を成熟させる
本日は、職員研修で今年度の成果と課題を教職員で出し合い、次年度に向けた課題を探る取組をしました。「教職員は」「生徒の学力は」「生徒の生活は」などいくつかに分けて分析しました。もちろん、多くの成果が確認できました。と同時に、多くの課題も出されました。このような個々の考えを出し合いながら協議を進めるには、一人一人がプロの職人として成熟していなければなし得ません。また一つ、教師としてさらに成熟する時間であったことを確認しました。
【校長室よりNo.174】雪に耐えて梅花麗し
週末の温かさから一変して、今日は雪景色となりました。正面玄関の梅の花を見て、西郷隆盛の言葉である「雪に耐えて梅花麗し」という言葉を思い出し、シャッターを切りました。梅の花は、厳しい寒さの後の春の訪れを感じさせてくれる花です。厳しい冬の寒さに耐えてこそ、より美しい梅の花が咲く。故に人間も多くの困難を乗り越えてこそ、美しく輝くと解することができるでしょうか。今週はいよいよ栃木県立高校入試です。厳しい時間を乗り越えた3年生が、見事な花を咲かせることを祈るばかりです。
【校長室よりNo.173】温かい言葉で始まる朝
週末の温かさから一変して、今朝は冷たい雨の降る朝でした。それでも、中村中の生徒たちは手を冷たい雨にさらしながらでも、一生懸命に自転車を漕いで登校してくれていました。「寒い中大変だったね。」と生徒たちに声をかけると、「ありがとうございます。」「校長先生こそ、寒くないですか?」と温かいお返事を返してくれます。どんなに冷たい雨が降っていても、温かい言葉で心が温まる朝でした。
【校長室よりNo.172】支えられていることを実感します
本日、今年度最後の授業参観として、1年生は通常の授業を公開し、2年生は先に実施したマイチャレンジの報告会を行いました。教室に入りきれないほどの多くの保護者の方々がご来校下さり、生徒の様子を見守って下さいました。保護者の方々もお仕事等でお忙しい中、こうして多くの方がご来校下さると言うことは、学校教育に対して高い関心を持って下さっており、それ故に多くの場面で支えていただいていることを実感します。
【校長室よりNo.171】PDCAサイクルによる学校教育の検証
PDCAサイクルという言葉は、様々な場所で耳にします。Plan(計画)Do(実践)(確認・振り返り)Action(行動・実践)を意味します。これを学校に当てはめると、今年度の学校行事を含めた様々な教育活動を振り返り、成果と課題を明確にします。成果となった部分は更なる高めへと導きます。課題となった部分は、来年度の教育活動に反映させます。下の写真は、そのための会議(作業)の様子です。それぞれの教員が持つ教育観念を出し合い、来年度、よりよい教育活動になるよう真剣に話し合いました。
【校長室よりNo.170】地域の宝
2月17日に、真岡市役所において中村中学校10名の生徒が、石坂市長様より感謝状をいただきました。12月24日に発生しました中村地域における枯れ草火災に際し、学校帰りの生徒10名が協力して自主的かつ迅速に消火活動をしたことへの感謝状でした。10名の生徒それぞれが市長様から感謝状を手渡されました。火災を発見したとき、119番通報をするだけで終わらせることもできたはずです。それでも、危険を顧みず、バケツや鍋までも持ち出し、全員で協力して鎮火させたことには大きな意義があると感じます。子どもたちは、家族や地域の方々の愛情に包まれて育つ。こうして育った子どもたちは、地域への愛情を持って、地域に貢献しようとする。そんな素敵な人の流れがこの中村地区にはあるということなのだろうと思います。子どもたちは地域の宝です。誤った行動をしているときは、愛情を持って注意してあげて下さい。そして、日頃から温かい言葉をかけてあげて下さい。こうして育った子どもたちが、今回のような「善行」をする人に育つのだろうと思います。
〒321-4351