校長室から
12月の朝会 校長講話〈豊かな心:心やさしく〉
12月4日~10日は「人権週間」です。そこで、「人権について考える」という
テーマで話をしました。
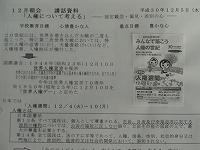

20世紀は2つの世界大戦があり、人権侵害、人権抑圧が横行しました。
そこで、国際連合では、1948(昭和23)年12月10日に世界人権宣言※を
採択しました。※世界における自由、正義及び平和の基礎である基本的人権を
確保するため、全ての人民と全ての国とが達成すべき基準
今年は世界人権宣言70周年
1950(昭和25)年12月10日を「世界人権デー」と定めた。
日本では「人権週間」は12/4(火)~10日(月)
日本国憲法第13条 ・・・・・・・生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利に
ついては、公共の福祉に反しない(正しく、自分のため、みんなのために)限り、
立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
○社会には様々な人権問題がある
最近で言えば、医学部入試で女子が不利になっていたこと・・・
栃木県人権施策推進基本計画から
女性 子ども 高齢者 障がい者 アイヌの人々 外国人 ・・・
☆学校、学級ではどうか、考えてみよう。
○なぜ差別が? 固定観念 偏見 差別 これらの意識を人はもっている
固定観念で考えてしまう話を紹介し、固定観念が自分にもあることを実感しても
らいました。
○日本とトルコの思いやりの連鎖について紹介しました。
1890(明治23)年 トルコの軍艦エルトゥールル号が和歌山県串本町沖で遭難
500名以上の犠牲者
串本町の住民が自分たちのために蓄えた食料を提供し、救護。
69名を救出 和歌山県知事から明治天皇に言上され、日本の
軍艦でトルコに送還
95年後
1985(昭和60)年 イラン・イラク戦争の最中 イラクのサダム・フセインが
「今から48時間後、イラン上空を飛ぶすべての飛行機を撃ち落とす」と、
発信。
イランには日本企業やその家族が住み、大慌て。テヘラン空港に向かうが、
どの飛行機も満席。日本政府は救援機の早い決定できず。
そこへ、2機の飛行機が到着。トルコ航空の飛行機だった。トルコ国民がいる
にもかかわらず、日本人215名全員を乗せて、成田に向けて飛んだ。タイム
リミットの1時間15分前だった。日本政府もマスコミも知らなかった。
前・駐日トルコ大使の談
「和歌山県沖のエルトゥールル号遭難事故に際し、串本町の人たちがして
くださった献身的な救助活動を、今もトルコの人たちは忘れていません。
私も小学生の頃、歴史教科書で学びました。トルコでは、子どもたちさえ、
エルトゥールル号遭難のことを知っています。今の日本人が知らないだけ
です。それで、テヘランで困っている日本人を助けようと、トルコ航空機が
飛んだんですよ。」
14年後
1999(平成11)年 トルコ大地震 先の215名が中心となって、日本中を
かけめぐり義援金を集め、トルコに送った。
12年後
2011(平成23)年 東日本大震災 トルコから各国に先駆けて応援部隊と
義援金、チャリティーバザー品が届く。トルコ政府やトルコ関係の組織から
援助金。
2011(平成23)年 トルコ南東部大地震 日本政府及び日本各地のNPOや
ボランティア団体が復興支援。
このように、人権を尊重し、助け助けられる学校・社会をつくっていきましょう。
テーマで話をしました。
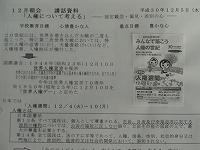

20世紀は2つの世界大戦があり、人権侵害、人権抑圧が横行しました。
そこで、国際連合では、1948(昭和23)年12月10日に世界人権宣言※を
採択しました。※世界における自由、正義及び平和の基礎である基本的人権を
確保するため、全ての人民と全ての国とが達成すべき基準
今年は世界人権宣言70周年
1950(昭和25)年12月10日を「世界人権デー」と定めた。
日本では「人権週間」は12/4(火)~10日(月)
日本国憲法第13条 ・・・・・・・生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利に
ついては、公共の福祉に反しない(正しく、自分のため、みんなのために)限り、
立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
○社会には様々な人権問題がある
最近で言えば、医学部入試で女子が不利になっていたこと・・・
栃木県人権施策推進基本計画から
女性 子ども 高齢者 障がい者 アイヌの人々 外国人 ・・・
☆学校、学級ではどうか、考えてみよう。
○なぜ差別が? 固定観念 偏見 差別 これらの意識を人はもっている
固定観念で考えてしまう話を紹介し、固定観念が自分にもあることを実感しても
らいました。
○日本とトルコの思いやりの連鎖について紹介しました。
1890(明治23)年 トルコの軍艦エルトゥールル号が和歌山県串本町沖で遭難
500名以上の犠牲者
串本町の住民が自分たちのために蓄えた食料を提供し、救護。
69名を救出 和歌山県知事から明治天皇に言上され、日本の
軍艦でトルコに送還
95年後
1985(昭和60)年 イラン・イラク戦争の最中 イラクのサダム・フセインが
「今から48時間後、イラン上空を飛ぶすべての飛行機を撃ち落とす」と、
発信。
イランには日本企業やその家族が住み、大慌て。テヘラン空港に向かうが、
どの飛行機も満席。日本政府は救援機の早い決定できず。
そこへ、2機の飛行機が到着。トルコ航空の飛行機だった。トルコ国民がいる
にもかかわらず、日本人215名全員を乗せて、成田に向けて飛んだ。タイム
リミットの1時間15分前だった。日本政府もマスコミも知らなかった。
前・駐日トルコ大使の談
「和歌山県沖のエルトゥールル号遭難事故に際し、串本町の人たちがして
くださった献身的な救助活動を、今もトルコの人たちは忘れていません。
私も小学生の頃、歴史教科書で学びました。トルコでは、子どもたちさえ、
エルトゥールル号遭難のことを知っています。今の日本人が知らないだけ
です。それで、テヘランで困っている日本人を助けようと、トルコ航空機が
飛んだんですよ。」
14年後
1999(平成11)年 トルコ大地震 先の215名が中心となって、日本中を
かけめぐり義援金を集め、トルコに送った。
12年後
2011(平成23)年 東日本大震災 トルコから各国に先駆けて応援部隊と
義援金、チャリティーバザー品が届く。トルコ政府やトルコ関係の組織から
援助金。
2011(平成23)年 トルコ南東部大地震 日本政府及び日本各地のNPOや
ボランティア団体が復興支援。
このように、人権を尊重し、助け助けられる学校・社会をつくっていきましょう。
0
芳賀地区児童生徒作品展を見てきました
12月1日(土)~2日(日)「道の駅はが」において、芳賀地区
児童生徒作品展が行われました。本校からも6人の生徒の
作品を出品しました。粘土を使って、好みのキャラクター等を
作製しました。一生懸命造ったと感じられる作品でした。

児童生徒作品展が行われました。本校からも6人の生徒の
作品を出品しました。粘土を使って、好みのキャラクター等を
作製しました。一生懸命造ったと感じられる作品でした。

0
11月 校長講話〈確かな学力〉


講話資料
11月7日(水)の朝会で、「知を磨く2」〈夢実現に向けて〉と題して、脳科学による「10代の
壁」の乗り越え方のヒントについて話をしました。
「10代の壁」とは、人には、7歳~15歳の子ども時代に、勉強や運動でつまずきやすくなる
壁があるということです。10代では、自分の性格や能力などを周りの友だちと客観的に比較
して「自分はそれほどできるわけではない」などと感じ、自信を失ったり、劣等感をもつように
なったりします。また、具体的思考が中心だったのが抽象的思考ができるようになる年齢で
もありますが、そこについていけず、落ちこぼれてしまうこともあります。例えば、算数では、
おはじきなどの具体物を使って習っていたものが、分数や分数同士の割り算が入ってきた
り、記号を使った数式が入ってきたりして、抽象的な思考が必要になってきます。
「10代の壁」を乗り越えるには、脳の中の「前頭前野」の発達が必要です。前頭前野が弱い
と、行動に対する結果がうまく予想できなくなります。前頭前野は大脳から送られてきた情報を
もとにして、よい結果をもたらすための行動を決定しています。前頭前野が弱いと、どんな行動
がよい結果につながるか、わからなくなります。自分が今している行動がどのような結果につな
がるか、わからなくなるということです。例えば、テスト前にゲームを少しやろうと思ってやりだし
たところ、長時間やってしまった経験はないだろうか。このような行動も前頭前野の未発達から
くるものです。
「10代の壁」を崩すには・・・
☆ 脳は「ことば」と「数」が好き!
黙読より音読 英語も音読する方が効果抜群 書く作業で脳は大いに活性化
コミュニケーションは脳全体が活性化
計算すると脳が活性化 ちょっと難しいを速く性格にするのも効果的(100マス計算)
※授業や学年で取り組んでいる「復習確認小テスト」「尊徳テスト」「基礎学力向上テスト」
に向けてしっかり家庭学習をして備え、結果を出そう!
☆ 家庭学習の習慣化が脳にリズムをつくる
脳を鍛える3要素
① 勉強・・・「学び」に強く勉める。
② 栄養・・・脳は大量にエネルギーを消費(1回の食事で4~5時間しかもたない)するの
で、朝食をしっかりとる。
③ 睡眠・・・脳は眠っている間に復習したり、記憶を整理する。夜更かしをしない。
0
10月朝会 校長の話〈健やかな体〉
「なぜ、睡眠が大切なのか?」というテーマで話をしました。
7月実施の保護者アンケートと9月実施の睡眠・朝食調査票の結果より
保護者アンケートでは、全学年とも睡眠や朝食がとれていると、肯定回答し
ている割合は90%を越えていました。睡眠・朝食調査票では、睡眠時間が
7時間以上の生徒の割合は、学年が上がるにつれて低くなっていました。
1年生:87% 2年生:75% 3年生:63%
朝食を毎日とっていると回答している割合は、1,2年生は90%を超えてい
ましたが、3年生は金曜日、土曜日に夜更かしをして、翌朝遅くまで寝てい
て朝食をとっていない人が7人いました。部活動がなくなり、土日に早く起
きる必要がなくなって、そのような生活になっていると推測できます。勉強
して寝るのが遅くなっているのとは違うようです。睡眠は一般的に7時間以
上と言われています(必要な睡眠時間には個人差があるとも言われている)。
睡眠不足によって成長ホルモンのメラトニンの分泌が減って、体の成長や
精神的な弱さ(辛いことから逃げる、イライラ等)にも影響しています。また、
朝食抜きは脳の発達を妨げ、記憶力や思考力が弱くなると言われていま
す。よりよい眠りのために次の3点をあげました。
①夜の過ごし方 就寝1時間前に部屋の明かるさを落とす。
就寝30分~1時間前になったらスマホ等の強い光は浴び
ない。
②朝食 メラトニンの原料となるアミノ酸「トリプトファン」を多く含む卵、
乳製品、大豆製品、肉類などを意識して食べる。
③短時間の昼寝 午後2時頃眠くなるのは自然なこと。机に突っ伏して15分く
らい眠るのがコツ。
睡眠時間をしっかりとった人の方が学習効率が上がり、学力が向上する。
効果的な学習法は、考える内容の教科を先にやって、次に暗記の必要な
内容の教科をやり、すぐに寝ることがよい。例えば、漢字を覚えることをや
って、次にテレビを見てしまうと、覚えたことが消えてしまう。それは、脳の
『海馬』という部分が物を覚える作業をつかさどっていて、寝ている間に覚え
た知識を整理する作業をしているからだそうです。『海馬』は寝ることによって
大きくなるそうです。睡眠不足は、『海馬』を縮めることになるそうです。
認知症の人の『海馬』は縮んでいるそうです。この勉強の組み立て法を実践し
てみてください。


話の前に表彰を行いました。

いつも真剣に話を聞いてくれています。
7月実施の保護者アンケートと9月実施の睡眠・朝食調査票の結果より
保護者アンケートでは、全学年とも睡眠や朝食がとれていると、肯定回答し
ている割合は90%を越えていました。睡眠・朝食調査票では、睡眠時間が
7時間以上の生徒の割合は、学年が上がるにつれて低くなっていました。
1年生:87% 2年生:75% 3年生:63%
朝食を毎日とっていると回答している割合は、1,2年生は90%を超えてい
ましたが、3年生は金曜日、土曜日に夜更かしをして、翌朝遅くまで寝てい
て朝食をとっていない人が7人いました。部活動がなくなり、土日に早く起
きる必要がなくなって、そのような生活になっていると推測できます。勉強
して寝るのが遅くなっているのとは違うようです。睡眠は一般的に7時間以
上と言われています(必要な睡眠時間には個人差があるとも言われている)。
睡眠不足によって成長ホルモンのメラトニンの分泌が減って、体の成長や
精神的な弱さ(辛いことから逃げる、イライラ等)にも影響しています。また、
朝食抜きは脳の発達を妨げ、記憶力や思考力が弱くなると言われていま
す。よりよい眠りのために次の3点をあげました。
①夜の過ごし方 就寝1時間前に部屋の明かるさを落とす。
就寝30分~1時間前になったらスマホ等の強い光は浴び
ない。
②朝食 メラトニンの原料となるアミノ酸「トリプトファン」を多く含む卵、
乳製品、大豆製品、肉類などを意識して食べる。
③短時間の昼寝 午後2時頃眠くなるのは自然なこと。机に突っ伏して15分く
らい眠るのがコツ。
睡眠時間をしっかりとった人の方が学習効率が上がり、学力が向上する。
効果的な学習法は、考える内容の教科を先にやって、次に暗記の必要な
内容の教科をやり、すぐに寝ることがよい。例えば、漢字を覚えることをや
って、次にテレビを見てしまうと、覚えたことが消えてしまう。それは、脳の
『海馬』という部分が物を覚える作業をつかさどっていて、寝ている間に覚え
た知識を整理する作業をしているからだそうです。『海馬』は寝ることによって
大きくなるそうです。睡眠不足は、『海馬』を縮めることになるそうです。
認知症の人の『海馬』は縮んでいるそうです。この勉強の組み立て法を実践し
てみてください。


話の前に表彰を行いました。

いつも真剣に話を聞いてくれています。
0
学力向上専門員訪問研修会〈確かな学力〉
第8回(昨年度から2年間の取り組み)学力向上専門員訪問研修会を実施しました。
今回の研修のねらいは、「とちぎっ子学力学習状況調査」(2年生実施)等の結果を
もとに分析した本校の学力面の課題を解決するために、授業をどのように改善して
いくかを学び合うことです。








3年2組の社会科の授業を、髙橋先生に公開してもらい、その授業をもとに次の2項目
について話し合いました。
①生徒の興味・関心を高め、主体的に学習に取り組む姿勢を育むために、ねらいを生
徒と一緒に決めていく方法について
②協働して学ぶ力の育成のために、問題文や相手の発表を理解することや考えを相
手にわかりやすく伝えるために書く力をつける方法について
今後も、自分の授業でそれらのことを意図して実践していくことを確認しました。
次回の学力向上専門員訪問研修会は12月12日に、保体と理科の授業を参観し合っ
て、授業改善、授業力向上を目指していきます。
今回の研修のねらいは、「とちぎっ子学力学習状況調査」(2年生実施)等の結果を
もとに分析した本校の学力面の課題を解決するために、授業をどのように改善して
いくかを学び合うことです。








3年2組の社会科の授業を、髙橋先生に公開してもらい、その授業をもとに次の2項目
について話し合いました。
①生徒の興味・関心を高め、主体的に学習に取り組む姿勢を育むために、ねらいを生
徒と一緒に決めていく方法について
②協働して学ぶ力の育成のために、問題文や相手の発表を理解することや考えを相
手にわかりやすく伝えるために書く力をつける方法について
今後も、自分の授業でそれらのことを意図して実践していくことを確認しました。
次回の学力向上専門員訪問研修会は12月12日に、保体と理科の授業を参観し合っ
て、授業改善、授業力向上を目指していきます。
0
