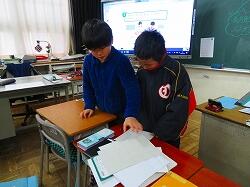文字
背景
行間
学校の様子
0206 1年道徳
1年生は、道徳で「友情、信頼」について考えました。
いつも仲良しの2人。そこに別な子が「一緒に遊ぼう仲間に入れて。」と言ってきました。さてさてどうするのでしょう。
「この段階においては,幼児期の自己中心性から十分に脱しておらず,友達の立場を理解したり自分と異なる考えを受け入れたりすることが難しいことも少なくない。しかし,学級での生活を共にしながら一緒に勉強したり,仲よく遊んだり,困っている友達のことを心配し助け合ったりする経験を積み重ねることで,友達のよさをより強く感じるようになる。」と言われています。
「さいこうのこ」のみんな、その主人公ならと話しているうちに、少しずつ自分だったらという意見が出てきました。
こういうときにどうするか、1年生は、思い悩みます。そして、様々な考えに触れることで、自分の考えを育ててきます。実際その場で判断するのは、本人自身です。
学校の教育活動の中で、友達のよさに気づけるよう、これからもつながりを大切にしながら、育てていきたいと思います。
0206 2年算数
2年生は、算数「1000より大きな数」の学習で、2300について理解を深めていました。
2300は、1000が2個と100が3個、100が23個、10が230個など考えていました。
子供たちは、「500が( )個と100が( )個と言える。」とか、「10000より( )小さい数」とか、「5が( )個の数」など、自分が気が付いた数の表現で、問題つくりもしていました。
数字を豊かにみることができるということは素晴らしいことです。
これは、大人になっても育てていかなければいけない感覚なので、これからも様々な考えに出会えるといいですね。
0205 小学校入学説明会
次年度入学してくる、新一年生に対して、小学校入学説明会を実施しました。
本校では、縦のつながりつくりや、小学校入学ギャップを減らすために、全児童と一緒に遊ぶ時間を設けております。
新一年生も楽しそうに参加することができました。
新一年生の皆さん、御入学をお待ちしております。
0205 昼休み
昼休みは、気温が低く、少し風花が舞いました。
そのような天気の中でも、元気に外で遊ぶ「さいこうのこ」のみんながいました。
その中、先生も一緒に遊んでいる姿が見えました。
0204 昼休み
今日は、3、4年生の投力王チャレンジでした。
前回より寒かったので、記録を伸ばすのは難しいかな?
最後に先生のチャレンジ。
子供たちは大喜び、遠くまでバックして守っていました。
0204 5年道徳
5年生は、道徳の時間に「節度ある生活」について話し合いました。
教材の主人公は、友達が買ったというジーパンが欲しくなってしまいました。でも、誕生日に洋服を買ってもらったばかりです。そのため、親も購入を認めません。その中で、心が動く主人公の様子をもとに話し合いました。
子供たちは、主人公の気持ちを考えながら、自分のことも振り返っている様子が伺えました。
高学年では、「児童一人一人が自分の生活を振り返り,改善すべき点などについて進んで見直しながら,望ましい生活習慣を積極的に築くとともに,自ら節度を守り節制に心掛けるように継続的に指導することが求められる。」となっています。
0204 縦割り共遊
今日の業間活動は、縦割り共遊の時間でした。
1~6年生まで、みんなで仲良く遊ぶことができました。本校の「いつも 笑顔あふれる たのしい学校」が表れた時間でした。
今日は、今年度最後の縦割り共遊の時間でした。
一年間お世話になった6年生に、みんなから感謝の言葉を伝えている場面がありました。
このような活動を通して、思いやりの心を育んできました。
0204 朝の様子
北海道や北陸など、広範囲で寒波の影響のニュースが流れていました。大きな事故などがないことを祈ります。
今朝は、きれいに晴れ渡り、児童は元気に登校してきました。
お気づきでしょうか?校舎の特徴でもある時計塔がリニューアルしました。今日からシートも外され、見ることができるようになりました。某番組で残念だった場所の時計塔です。
これから「さいこうのこ」のみんなを見守ってくれることでしょう。
0203 昼休み
寒空の中でしたが、「さいこうのこ」のみんな、元気に遊んでいました。
1・2年生と一緒に遊んでくれている6年生もいました。大内西小学校の良さですね。
0203 4年算数
4年生は、算数で「立体」の学習をしていました。
ICTを使って学習を進めることもできますが、実際に手を動かして考えることも、小学校教育では大切にされています。
実際に、工作用紙を利用して、立方体や直方体を作っていました。
ほとんどの児童が、面を六面切り取って作っていましたが、中には、展開図のように考えている児童もおり、このような考えの違いは、実際に工作用紙などを使って作らないと生まれません。そうすることで、違う見方が育ち、深い学びへとつながっていきます。